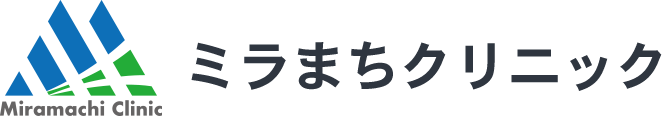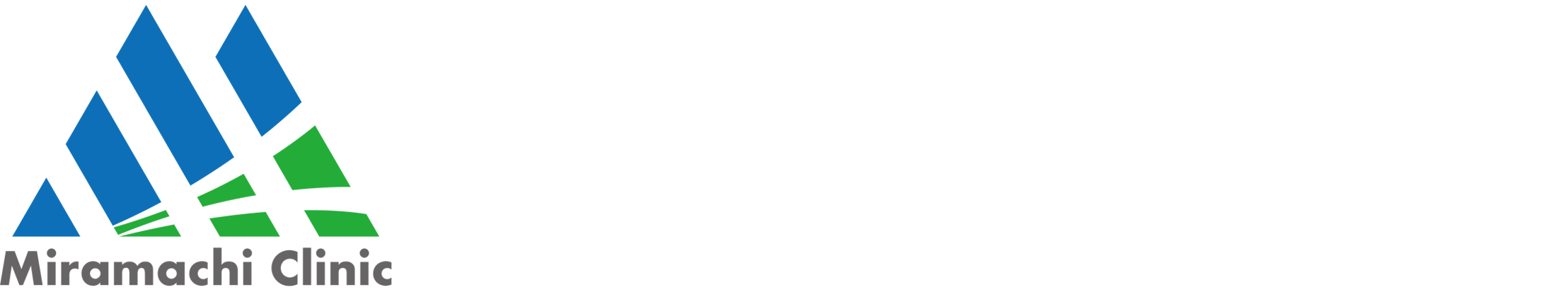虚血性心疾患(心筋梗塞・狭心症)
心臓に血がいきわたっていない状態を
「虚血性心疾患」といいます。
心筋梗塞は、心臓の筋肉が壊死する重大な病気であり、適切な治療を迅速に受けることが非常に重要です。
労作性狭心症の段階では、心臓の筋肉が壊死に至っていない場合が多く、この段階で診断・治療ができれば、その後大きな後遺症なく生活していけることが多いですが、治療せずに放置している場合、不安定狭心症や急性心筋梗塞に進展してしまう危険性があります。
思い当たる症状のある方は早めの診察をおすすめします。

急性心筋梗塞
心臓の筋肉に酸素や栄養を送っている冠動脈という血管が閉塞して、心臓の筋肉が壊死する病気です。通常、血栓(血の塊)によって、冠動脈が閉塞します。
心筋梗塞になると、致死的な不整脈や心破裂、心不全を引き起こし、死に至る危険があります。
発症後入院するまでに死亡する人を含めると、心筋梗塞の死亡率は40%程度になると考えられますが、入院後に死に至る危険は10%以下です。
症状
強い胸の痛み、押さえつけられる感じ、締め付けられる感じ、冷や汗、息苦しさ、吐き気などが、突然出現して20分以上続きます。
ただし、高齢者や糖尿病がある場合には、比較的軽い症状しかないこともあります。
検査
心電図で診断できることが多いですが、正常な時の心電図と比較しないとわからない場合もあります。
血液検査では、発症からある程度時間が経たないと、異常が出ませんが、繰り返して検査することで診断できます。
疑いが強い場合には、心臓カテーテル検査によって診断し、そのまま治療を開始します。
治療
経皮的冠動脈形成術(PCI)といって、狭心症のカテーテル治療と同様ですが、心筋梗塞では閉塞している冠動脈を一刻も早く再開通させることが一番の目的です。
カテーテルを使って、血栓を吸引除去したり、バルーン(風船)やステント(金属のコイル)で血管を広げます。
再閉塞を予防するために、2種類の抗血小板薬(血液を固まりにくくする薬)を服用します。
不安定狭心症
心臓の筋肉に酸素や栄養を送っている冠動脈という血管が詰まりかけて、心臓の筋肉に十分な血液が届かずに酸素不足になる病気を狭心症と言いますが、その中でも心筋梗塞になる危険性が高い状態のものを不安定狭心症と言います。
これは心筋梗塞の前兆とも言えます。
症状
これまでなかった胸の痛み、圧迫感、絞扼感、心窩部痛、胸焼け、腕・肩・顎・歯の痛みなどの症状が出現するようになります。
症状は比較的軽度で、数分、10分程度で消失しますが、繰り返し出現することが多いです。
労作時に出現することも、安静時に出現することもありますが、安静時に出現する場合、持続時間が長くなってくる場合、出現頻度が多くなってくる場合は、心筋梗塞へ移行する危険性が一層高いです。
検査
心電図、血液検査、心臓超音波(エコー)検査で異常があれば診断できますが、これらの検査では異常がないことも多いです。
より精密な検査としては、冠動脈CT検査がありますが、造影剤を使用するため、腎臓の悪い人ではさらに腎臓が悪くなって透析が必要となる危険性があります。
最終的には、心臓カテーテル検査によって診断し、そのまま治療を開始します。
治療
経皮的冠動脈形成術(PCI)といって、一般的な狭心症のカテーテル治療と同様です。
カテーテルを使って、バルーン(風船)やステント(金属のコイル)で血管を広げます。
再閉塞を予防するために、2種類の抗血小板薬(血液を固まりにくくする薬)を服用します。
労作性狭心症・無症候性心筋虚血
心臓に血液を送っている血管(冠動脈)に動脈硬化を生じ、狭くなった(狭窄)ために、心臓の筋肉に必要な血流が届いていない状態を虚血と言います。
特に労作時にはより多くの血流が必要になるのですが、冠動脈の狭窄のために、心臓の筋肉に必要な血流が届ずに生じる胸部症状を労作性狭心症と言います。
またご高齢または糖尿病をお持ちの方は、心臓の筋肉が虚血状態にあるにもかかわらず、症状を自覚しないことがあり、無症候性心筋虚血と言います。
症状を自覚しない無症候性心筋虚血であっても、労作性狭心症と比較して、予後は同等・またはより不良というデータもあり、無症状であっても精査・加療が必要です。
労作性狭心症の段階では、心臓の筋肉が壊死に至っていない場合が多く、この段階で診断・治療ができれば、その後大きな後遺症なく生活していけることが多いですが、治療せずに放置している場合、不安定狭心症や急性心筋梗塞に進展してしまう危険性があります。
症状
胸部前面を中心に、圧迫感・絞めつけられるような感じ・つまるような感じで,一本指で指すことのできない漠然とした痛みが典型的な症状です。
身体的労作(坂道や階段を昇る、仕事や家事、入浴など)が誘因となって胸部症状が現れ、安静やニトロペンなどの硝酸剤によりほとんどが数分から10分以内で改善します。
時に上腹部や左肩、または首や顎に広がる症状を呈することがあり、放散痛と言います。
このため患者さんによっては「胃が痛い」、「歯が痛い」と言う症状で病院に来院されて、狭心症の診断を受けることもあります。
検査
冠動脈に狭窄があっても安静では必要な血流が確保されているため、安静時に行う心電図などの検査では異常を検出できないことが多いです。このため、検査の際には運動または薬剤による負荷検査が有用です。
一般に負荷心電図、トレッドミル検査、負荷心筋シンチグラムで虚血の検出が可能です。
最近では造影剤を用いた心臓CTを撮像することにより冠動脈の狭窄を発見される機会が増えています。
これらの検査から労作時狭心症または無症候性心筋虚血が疑われた際には、待機的に心臓カテーテル検査目的に入院いただく必要があります。
治療
一般に冠動脈の狭窄に対する治療法として、カテーテルによる治療(経皮的冠動脈形成術:PCI)、外科的手術による冠動脈バイパス手術、または内服加療、の選択肢があります。
より効果的に心臓の筋肉への血流を増加させる方法としては経皮的冠動脈形成術、または冠動脈バイパス手術による血行再建術があり、患者さんの病変箇所・病変形態により、どちらが適切な治療法かを判断します。
経皮的冠動脈形成術(PCI)はカテーテル(細長い管)を用いて血管内から治療を行い、バルーン(風船)やステント(金属のコイル)で血管の狭窄部位を広げます。
動脈硬化が進展し石灰化を含む病変に対しては、ドリル(ロータブレーター)で石灰化病変を削ることもあります。
血管内から治療を行うため、患者さんへの侵襲が少ないです。
ただしより重症な病変の場合や他の心臓のご病気(弁膜症など)をお持ちの場合は、冠動脈バイパス手術が必要となることもあります。
また、狭窄部位を治療後にも、今後の狭窄の新規出現または再発を予防のために、動脈硬化の危険因子である、高血圧・脂質異常症・糖尿病に対する治療の継続と禁煙が必要です。
冠攣縮性狭心症
冠動脈に器質的な狭窄がないものの、発作的に血管に含まれる筋肉に痙れん(れん縮・スパズム)が起こり、一時的な狭窄を生じるために、心臓の筋肉が虚血状態になり生じる病気を冠攣縮性狭心症といいます。
原因として、喫煙、飲酒、脂質異常症、ストレスなどがあり、動脈硬化との関連性も示唆されています。ほとんどは一過性の発作であり、時間とともに改善を認めますが、時に攣縮が持続して心筋梗塞に進展することもあります。
狭心症としては上記の労作性狭心症と比較して稀なために「異形狭心症」と言われることもありますが、発症頻度は欧米人よりも日本人に多いと言われています。
症状
胸部症状については労作性狭心症と同様ですが、労作性狭心症とは異なり、労作時よりも安静時、特に夜間から早朝にかけて生じることが多いです。
過呼吸や飲酒により誘発されることがあります。
ニトロペンなどの血管拡張剤が著効するのも特徴です。
検査
運動負荷検査では発作が誘発されないことが多く、24時間心電図を記録するホルター心電図で診断されることがあります。
また、入院して心臓カテーテル検査中に、薬剤(アセチルコリン・エルゴノビン)により発作を誘発する負荷試験により診断されることもあります。
治療
冠動脈に狭窄がなければ、バルーンやステント治療ではなく、発作を予防する目的で血管拡張剤の内服加療が治療の中心となります。
また発作を誘発する原因の是正、禁煙、血圧管理、糖尿病や脂質異常症の是正、過労や精神ストレスの回避、節酒が必要です。